こんにちは、アシリパです。
喜多川 泰さん著の「君と会えたから……」を読みました。
この本の物語は、自己啓発本のような「教訓」が織り交ぜられたストーリー構成になっています。
「自己啓発小説」というジャンルにあたるようですが、小説×自己啓発の相乗効果が素晴らしく、小説を読むのが苦手な私ですが、最後までサラッと読めてしまいました。
またこの本の中で語られる「教訓」は、中堅サラリーマンの私に深く刺さる内容でした。
そこで本記事では、この本の物語についてネタばれしない程度に紹介しつつも「教訓」については「中堅サラリーマンの私がどう感じたのか」の視点を入れながら解説したいと思います。
作中ヒロインのハルカから語られる「教訓」はどれもまっすぐでシンプルで、それでいて温かいものです。
私のように「教訓」から勇気をもらえた読者さんが本記事を通して増えれば嬉しいです。
それでは解説していきます。
作品情報
君と会えたから……
著者:喜多川 泰
自己啓発小説ですので小説を読むのが苦手な方にもオススメできる一冊です。過去に「嫌われる勇気」や「夢をかなねるゾウ」を読んだことがある方でしたらサクッと読めてしまう内容かと思います。なんか言葉にできない「漠然とした不安」が今あるようでしたら、試しに読んでみることをぜひおススメします。
物語としてのあらすじ
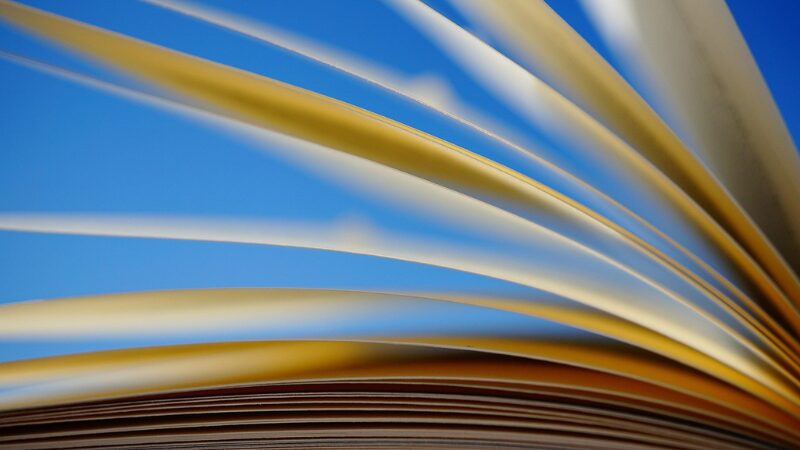
高校2年生の夏休み。主人公のヨウスケが少し不思議な少女のハルカと出会うことから物語が始まります。
父が営む書店を手伝っていたヨウスケ。そこへ透き通る白い肌に白いワンピースを着た少女が訪れます。
この書店の雰囲気とは似合わないほど美しい女の子です。
「一冊の本を注文したい」。
少女は店番のヨウスケへそう伝えます。
「お取り寄せの本ですので入荷しだいお渡しします」と事務的な返事をする一方で、ヨウスケは一瞬にしてハルカに恋心をいただきます。
そして同時にハルカが注文した一冊の本が気になってしまいました。
後日、父の計らいでたまたまその本を手にしたヨウスケはさっそく中身を見てみます。
その本の中身は、今まで読書をしてこなかったヨウスケにとって衝撃的なものでした。
「決して冷めない狂おしいほどの情熱を持って行動を起こせ」
このようなことが何回も書かれた本でしたが、将来へ漠然とした不安があるものの何も行動を起こせず無気力に毎日を過ごしていたヨウスケにとっては内側に少しの革命が起こるほどの内容でした。
それからこの本がきっかけとなってヨウスケはハルカと頻繁に会うようになります。
そしてヨウスケはハルカに色んなことを話します。
これからのこと、将来のこと、夢のこと、しかし今は何もやれていないことで不安があることなど、ハルカに話します。
ハルカはそんなヨウスケの話を聞いた後に、パパから教わったある教えを伝えます。
その教えとは、ヨウスケにとってどれも新しくて本質的でそれでいてどこか温かいものでした。
ハルカからその教えをもらうことで、ヨウスケは徐々に考え方や行動が変わっていきます。
そしてそんなハルカのことをもっと好きになっていきます。
しかし、そんな大切な時間は突然終わりを迎えます。
ハルカにはヨウスケが知らない隠された秘密があったのです。
ハルカが伝える教訓

物語のなかでハルカがヨウスケに語るのは、人生を成功に導くための「7つの教訓」です。
ヨウスケはこれに衝撃を受けて、毎日少しずつ実践し続けます。
すると毎日が良いように変わっていくのです。
この「7つの教訓」はどれも私たちの心にも深く響くと思います。
なぜなら、ヨウスケが抱える「将来への不安や、行動したいけど行動できないもどかしさ」は誰もが過去に経験することですし、今まさに抱く感情だからです。
中堅サラリーマンとして働く私自身にもこれらの教訓は心に刺さりました。
「出世競争に挑戦するべきか」
「今と同じ仕事のまま働いて良いのか」
「いっそ転職して環境を変えるべきか」
変化のない未来へ危機感を持ちつつも、今いる環境の安心感から抜け出せない私が、もう一度未来を考えようと勇気をもらえました。
ここからはその教訓について具体的に3つをご紹介していきます。
- ライフリストを作る
- 目標達成の方法は1つじゃない
- 可能を不可能にしてしまう恐ろしい敵がいる
【教訓①】ライフリストを作る

まずはじめは、「2つのライフリストを作る」ことです。
1つ目のライフリストには「自分の人生で達成したいと思えること」を書いていきます。
そして2つ目のライフリストには「自分の人生のなかで他の人にやってあげたいこと」を書いていきます。
ハルカは1つ目のライフリストを「TAKEのリスト」、2つ目のライフリストを「GIVEのリスト」と呼んでいます。
| TAKEのリスト | GIVEのリスト | |
|---|---|---|
| 内容 | 自分の人生で達成したいこと | 自分の人生のなかで他の人にやってあげたいこと |
| 書くこと | 行ってみたい場所、やってみたいこと、 実現したい夢、就いてみたい職業など | 他の人が今よりも幸せになるために 自分が今からできること |
| たとえば | 世界一周の旅をしたい、野球選手になりたい | 一日一回家族を笑わす、困っている人を勇気づける |
「TAKEのリスト」と「GIVEのリスト」は表裏一体の関係になっています。
つまり「自分がこうしたい、こうなりたい」という夢や目標のTAKEリストは、「他の人にこうやってあげたい」というGIVEリストの行動の結果になっています。
たとえば、TAKEリストに「世界中でヒットする商品を開発して特許を取る」、GIVEリストに「母親の負担を少しでも軽くしてあげたい」と書いたとします。
洗濯機を例に出すと、洗濯機はある人が妻の負担を少しでも軽減したい(GIVE)という強い情熱のもとで商品開発されて誕生した(TAKE)という背景があります。
このように、GIVEの行動の結果がTAKEの実現になっています。
ここで大切なのは、TAKEリストは結果として手に入るものであって、それを目標にして生きるものではなく、GIVEリストに書かれた「そのために今日何ができるか」を考え実践することです。
TAKEリストに比べると、GIVEリストは短期・中期・長期的な視点で具体的に書く必要があるためかなりの時間がかかります。
しかしこれを実際に行なってみると、自分のなかでこれまでボヤっとしていた「軸」や「そのために今何の行動をとれば良いのか」がハッキリしてきます。
私のライフリスト
私が今行動すべきなのは家族を幸せにすることです。
ライフリストを実際作ってみて、中堅サラリーマンとして今ここにいることがGIVEとTAKEに本当になっていることなのかが少しですが分かったような気がします。
【教訓②】目標達成の方法は1つじゃない

次は、「手段を目的にしない」ことです。
「教訓①」では「TAKEのリスト」に自分の人生で達成したいことを書こうとお話ししました。
そしてそのなかには、「将来こうなりたい、こういった職業に就きたい」などの夢も含まれているかと思います。
しかしそれらは、今から実現させることが年齢的にも才能的にも難しいものが含まれているはずです。
現実的には仕方がないことですが、ここで大切なのは「ある職業に就くことは自分の夢を実現するための1つの手段でしかない」という考え方です。
たとえばTAKEのリストに「将来の夢は野球選手になること」と書いたとします。
そして実際に野球選手になれたとして、その人が野球選手になることで手に入れたかったものがすべて満たされているわけではありません。
現実的には野球業界で活躍している方はほんの一握りですし、その裏には実績を残すことができず今を悲観している方、躍起になっている方がたくさんいるはずです。
しかし「どうして野球選手になりたいのか」という問いを改めて考えてみると、その目的は多くあったことに気づきます。
「お金をたくさんもらいたい」「大好きなことをしたい」「人に勇気を与えたい」などの目的があるはずです。
つまり、その人にとっての夢というのは、「野球選手になることではなく、そういうことができる人になること」なのです。
そして、今から野球選手になれなくても、そういうことができる人になる方法は世の中にたくさんあります。
たとえば、お金をたくさんもらいたいのなら起業して成功するのも一つの方法です。
大好きなことをしたいのなら野球選手になる以外の業界の関わり方もあるはずです。
このように職業を目指すことは1つの手段であって、その裏の「自分がそうしたい本当の目的は何か」を考えることが重要です。
そしてそれがハッキリしたら、その目的地に行くことを諦めずに必死になることが人生成功の秘訣です。
社内の肩書や地位
出世競争の狭間にいる中堅サラリーマンの私にとって「教訓②」は大事な考え方でした。
たしかに今の私に「この会社でこんなことを成し遂げたい」という目的があるのならば、それを実現する権限のある役職を目指すことは理にかなっていると思います。
しかし今の私にそのような志があるのかどうか。それよりも優先すべき自分の人生のなかでなりたいこと、やりたいことがまだまだあるような気がします。(まだまだTAKEリストの深堀りができていませんね。)
社内の肩書きや地位にこだわることが、自分が目指す目的の本当の手段になりうるのかは改めて考えなくてはいけないなと思いました。
【教訓③】可能を不可能にしてしまう恐ろしい敵がいる

最後の3つ目は、「できないという先入観を捨てる」ことです。
人生の成功に向けて日々努力を続けたとしても心のなかには、「どうせ自分なんてできっこない」と思うことがあるかもしれません。
人間は固定観念に縛られる生き物です。
少し何かをミスしただけで、「自分はできない人間なんだと」すぐに決めつけてしまいます。
物語のなかでハルカは次のように語ります。
「昨日までできなかったという事実が、今日もできないという理由にはならない」
「人生のなかの20年ができなかったからと言って、自分はできないわけでは決してなく、もしかするとその後の5年後にできるようなるかもしれない」
この言葉は、固定観念に縛られることで、自分の可能性を閉ざしかねないことを示唆しています。
私も昔は人と話すのが苦手で、「自分はコミュ障なんだ」と勝手に決めつけていた時期がありました。
しかし会社で営業職に就いて、毎日たくさんの人たちと話すことで、その悩みは自然と解消されました。
この本がきっかけで、この経験が今の自分を大きく変えたと思い返すと同時に、固定観念の怖さを改めて認識できました。
中堅会社員の私の固定観念
「自分は今の環境から抜け出すことができない」
「自分は管理職にはなれない」
中堅社員として長く働いていると、会社から「マネジメントを少しかじっているプレイヤー」と評価されるようになります。
その結果、今の職場や業務の役割は、自分にしかできないものとつい錯覚してしまうことがあります。
しかし、それこそ私自身の未来の可能性を閉ざしている固定観念です。
長く同じ環境・立場にいる人は特に、「この固定観念にとらわれていないか」、「挑戦することを諦めていないか」を改めて自問自答する必要がありますよね。
感想
この本を読んでから著者が運営されているサイトやインタービュー記事を見に行きました。
喜多川さんは、「1冊との本との出会いで人生は変わる」とオフィシャルサイトで語っているように読書の素晴らしさを世の中に伝える活動もされている愛媛県出身の作家さんです。
あるインタビュー記事のなかで「本を読むことは志を芽生えていくこと」だと話されていました。
「志」とは、将来未来自分はどんな人になりたいか、どんな一生を送りたいかということ。そこには「夢」のように「こうなりたい、あぁなりたい」というような個人的な未来の含みもありつつも、どちらかというと「世の中、社会で自分はこうなりたい」というようなより具体的な言葉のニュアンスがあります。
つまり喜多川さん曰く、「本を読むとは世のため人のために自分はどうなりたいかという意識を醸成されていく行為」になるそうです。
私たち人間はこうなりたい、ああなりたいなどの夢を持って生きる生き物です。
そして夢は尽きないものですし、勝手に自生していくものです。
ただし志は自分で育てていかなければいけません。
自分が未来に向けてどう挑戦していきたいかなどは自分で探すしかありません。
そしてその探す手段の一つが読書なのです。
この本のなかでも「夢」「将来」「人生」などのパワーワードが何回も出てきますが、ヨウスケとハルカの出会いのきっかけは、著者が掲げているテーマと同じ、1冊の本でした。
「ヨウスケを変えた1冊の本、ハルカを支える1冊の手記」
ここには作者の「読書」に対する愛が隠れているのかもしれませんね。
最後までお読みいただき、ありがとうございました。
これからもブログの記事向上に向けて投稿を続けていきます。
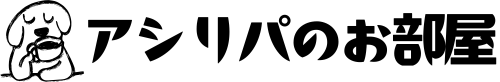
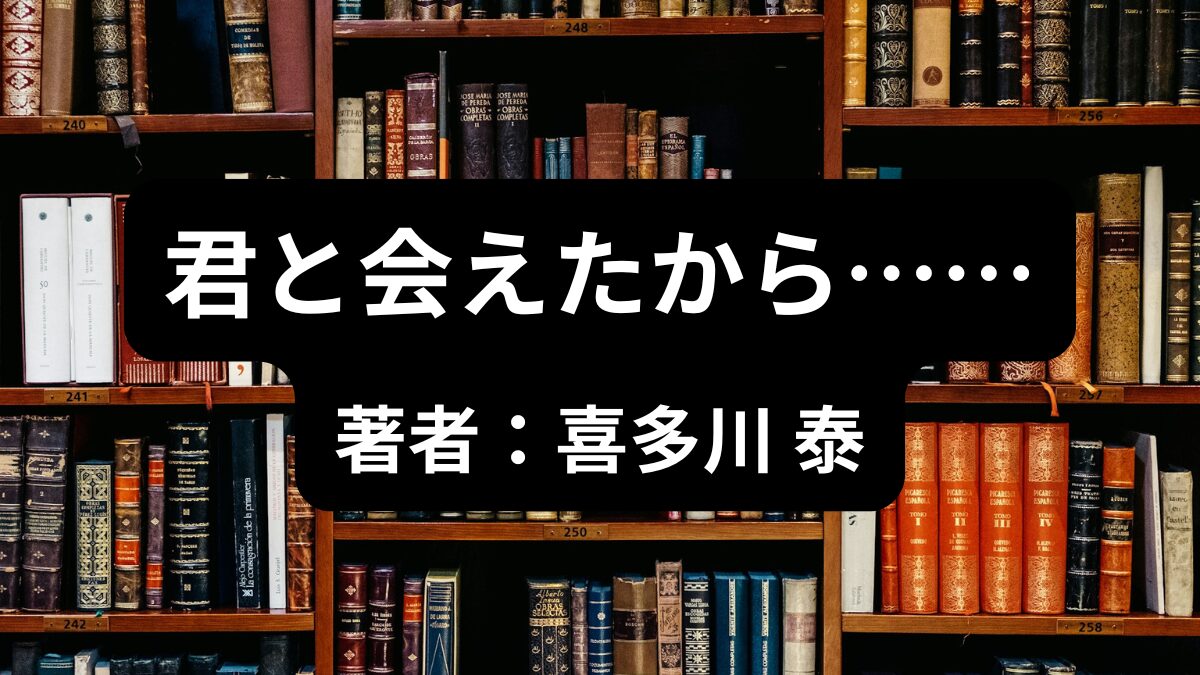



コメント