こんにちは、アシリパです。
マネジメントの知識も経験もないのに、会社からチームリーダーを任された経験はありませんか?
会社は本人の成長のためにと思ったのかもしれません。
しかし、マネジメントを全く知らない状態で、チームを運営していくのは大変なことです。
私は入社2年目に、社内プロジェクトのチームリーダーを任されたことがあります。
そのプロジェクトでは、私と年齢がひと回りもふた回りも離れた先輩社員たちがいるチームをマネジメントして、成果物を上げるものでした。
当時の私は、マネジメントの知識も経験も全くありませんでした。
しかし何とかチームをまとめようと毎日必死でした。
最終的には、期日までに間に合いましたが、精神的にも肉体的にも大きく疲弊したのを覚えています。
今思うと、マネジメントの知識が少しでもあれば、そこまで苦労することはなかったのかなと思います。
そこで今回は、「マネジメント知識0の新任リーダー」におススメしたい一冊をご紹介します。
本記事では、その本のなかから「新任リーダーがチームマネジメントをするうえで、まず覚えておきたい大切なこと」について解説します。
これを知っておけば、はじめてのチームマネジメントへの抵抗感がなくなるはずです。
それでは、さっそく見ていきましょう!
作品情報
リーダー1年目のマネジメント大全
著者:木部 智之
イラストや図解がたくさん使われていますので、誰でも読みやすい一冊だと思います。
タイトルが「大全」なだけあって、チームマネジメントについての基礎知識から、リーダーが直面する困りごとの対処法まで細かく、かつ具体的に解説されています。各節が独立した本の構成になっていますので、目次から気になるところだけを見つけて読む方法もおススメです。
リーダーのミッションは「ビジネス成果」と「人材育成」
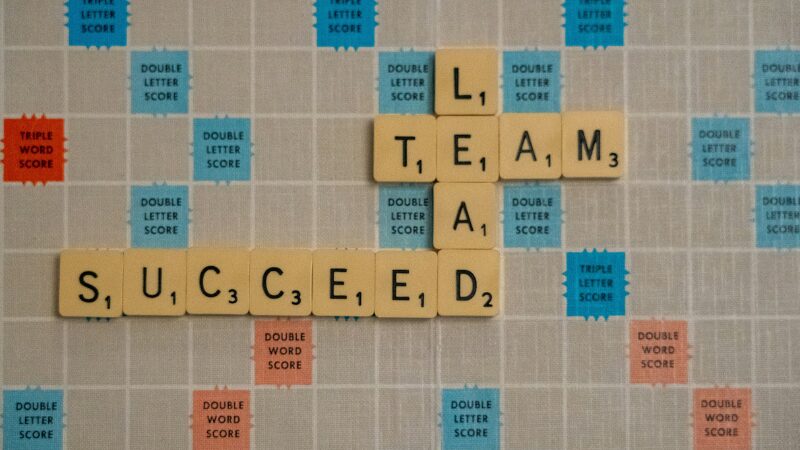
まずはチームリーダーがやるべきことについて解説します。
新任リーダーにいざなると「リーダーがやるべき仕事はたくさんあって大変だ。。」とつい思ってしまいますが、実はリーダーが行う仕事はシンプルに次の2つだけです。
リーダーが行うすべての仕事は、この2つの考え方が軸になります。
極端な言い方をすると「この考え方が当てはまらない仕事はリーダーのタスクではない」とも言えます。
会社のなかの自分が置かれた環境にもよりますが、
たとえば「プレゼン資料作り」「取引先との接待の幹事」「会議の議事録作り」なども、この2つの考え方が当てはまらなければ、リーダーが行う仕事ではありません。
したがって、新任リーダーは、まずはこの2つの考え方を頭に入れることが大切です。
そして、新任リーダーはこれから行おうとしている仕事がこの考え方に当てはまるのか、当てはまらないのかを常に判断していく必要があります。
私がはじめて新任リーダーをした当時は、この考え方を知らず、すべての仕事を片っ端から引き受けてました。
もちろんオーバーワークでパンクしましたが、
当時の私が「リーダーが行う仕事とは何か」というこの考え方を理解しておけば、こうはなりませんでした。
考え方の軸がしっかりすれば、リーダーの行動や立ち振る舞いが自然と安定します。
そして、それはチームメンバーへの接し方や信頼関係にもつながっていきますし、何よりリーダー自身の業務負担の軽減にもなるのです。
与えられた環境でビジネス成果を最大化させる
ここでは、「ビジネス成果の最大化」について解説します。
まず大事なことですが、リーダーは「組織の成果にコミットする」責任があります。
「メンバー同士のコミュニケーションが活発化した」「チームで大きい案件を獲得できた」
これはチームとしての良い結果やプロセスにあたりますが、ビジネスとしての成果でなければリーダーの責任です。
成果とは単に売上や利益だけを指すのではなく、新規サービスの立ち上げや社内サービスをトラブルなく運営していくことも成果になります。
リーダーはチームの成果を最大化するために日々努力しなければいけないのです。
そして、成果はリーダーの「戦略と実行力」で大きく変わっていきます。
どんなにチーム予算が潤沢でも、優秀な人材がチームにいようとも大きな成果が出るとは限りません。
逆に予算が少なくて、メンバーのスキルや人員が少なくても的確な戦略とそれを推し進める力があれば、大きな成果を出すことは可能です。
新任リーダーは「自分が置かれた環境での成果とは何か」、また「成果を上げるためにどのような戦略が必要でどう実行していくか」を日々考えて実行し続ける必要があります。
ビジネスでは数字=成果が命です。
新任リーダーは、個の成果よりもチームの成果を第一に考えて、結果を出さなければいけない立場にあることを覚えておきましょう。
チームメンバーのキャリアと人生設計に貢献する
次に「人材育成」について解説します。
リーダーはチームの成果を出す責任がありますが、
チームも組織も継続的に成果を出すためにはメンバー全員がレベルアップしていく必要があります。
戦国武将が兵士を鍛えて強い軍を作るように、ビジネスでもリーダーがメンバーを育てて強いチームにしなければ結果を出し続けることはできません。
また、リーダーはメンバーのキャリアと人生を預かる立場でもあります。
メンバーは、そのチームでの仕事を通して、自分自身のスキルやキャリアアップを行っていきます。
そのため、リーダーはメンバーの未来に向けた最良の道筋を作ってあげる責任があります。
「今のチームだと成長できないなぁ」とメンバーに思われないように、
メンバーをスキルアップさせて成果を上げさせるだけでなく、ステップアップさせて給料を上げてあげること。
そうしてメンバーの人生をより良くする責任がリーダーにはあるのです。
リーダーが行う4つのマネジメント

ここまではリーダーの考え方の軸について話してきましたが、
ここからは具体的なリーダーのマネジメントの仕方について解説していきます。
リーダーが行うマネジメントは、大きく4つに分けることができます。
- メンバーマネジメント
- チームマネジメント
- ビジネスマネジメント
- セルフマネジメント
| 項目 | マネジメント対象 | 具体的な仕事 |
|---|---|---|
| ① | メンバーマネジメント | メンバーへの仕事の割り振り、育成、キャリア支援、メンタルケアなど |
| ② | チームマネジメント | 仕事のアサイン、チームビルディング |
| ③ | ビジネスマネジメント | 戦略立案や実行、進捗管理など |
| ④ | セルフマネジメント | リーダー自身の成長とキャリアアップ |
リーダーは年間を通して「チームの成果と人材育成」を軸に、この4つのマネジメントをバランス良く回していくことになります。
次からはそれぞれのマネジメントの仕方について詳しく解説していきます。
①メンバーマネジメント:メンバーに合わせてコミュニケーションをとる
新任リーダーになってまず困るのが、メンバーマネジメントではないでしょうか?
個性も能力も自分との年齢も違うメンバーとうまくコミュニケーションをとって、メンバーを育成し成長させていくこと。これはなかなか難しいことですが、マネジメントでのコミュニケーションは特に重要な要素です。
ここではそれをうまくこなす方法について解説します。
メンバーのタイプをざっくり把握する
メンバーとのコミュニケーションでは、メンバーのタイプを知ったうえでタイプに合わせてコミュニケーションをとることが大切です。
なぜなら、メンバーとのコミュニケーションの巧拙でチームの成果が変わってしまうからです。
たとえば、協調性がないメンバーに「もっとチームと仲良くしましょう」とコミュニケーションをとったことで、そのメンバーから反感を買うかもしれません。
スキルがないメンバーに「重要なタスクを任せます」とコミュニケーションをとったことで、チーム全体の仕事の進捗に影響を与えるかもしれません。
このようにメンバーを知らずに闇雲にコミュニケーションをとってしまうと、チーム全体によくない影響を及ぼしかねません。
そこでおススメしたいのは、メンバーのタイプをざっくり分類し把握することです。
たとえば次の表のように分類します。
| 項目 | Aさん | Bさん | Cさん | Dさん | Eさん |
|---|---|---|---|---|---|
| スキル | 高 | 中 | 低 | 中 | 高 |
| ポテンシャル | 高 | 低 | 高 | 中 | 高 |
| 向上心 | 高 | 中 | 低 | 低 | 高 |
| 明るさ | 明 | 明 | 暗 | 明 | 明 |
| 積極性 | ポジティブ | ポジティブ | ネガティブ | ポジティブ | ネガティブ |
| 社交性 | 高 | 高 | 低 | 高 | 低 |
| 協調性 | 高 | 高 | 低 | 中 | 中 |
本書では項目を7つ設けてタイプ分けする方法を紹介されています。
タイプ分けで重要なことは、評価はシンプルに行うことです。
なぜなら、メンバーの考え方や行動は環境によって変化し続けるからです。
表は変化に合わせて柔軟に変更していきましょう。
このように、メンバーを事前にタイプ分けしておくと、コミュニケーションを取るときも、内容やタイミングによってどこの項目を意識すべきかが分かってきます。
たとえばチームのサブリーダーをメンバーの誰かに任せようと思ったときに、ポジティブなAさんとネガティブなCさんとでは、相談の仕方が変わってくるはずです。
メンバーのタイプを自分なりに「見える化」させて、メンバーとのコミュニケーションの参考にしてみましょう。
年上メンバーは特にうまくコミュニケーションを取る
新任リーダーであれば、メンバー全員が年上になるはずですからコミュニケーションは相当気を遣ってしまうはずです。
しかし、リーダーの立場と年齢の上下は別で考えなくてはいけません。
なぜなら、「年上だから気を遣う、やりにくい」という感情と、リーダーがやるべき業務は別次元のものと割り切らなければ、チーム全体をマネジメントすることができないからです。
もし年上メンバーとコミュニケーションがしにくいのであれば、「リスペクトすること」を念頭にコミュニケーションを取ってみましょう。
「すみません、いろいろと教えてください」と素直に自身の力不足を認めて、頼りにすることが年上メンバーとのコミュニケーションのコツです。
新任リーダーよりも年上メンバーの方が、スキルも経験も間違いなく豊富です。
戦略の要になる年上社員は、恐れずにリスペクトスタンスでコミュニケーションを図っていきましょう。
②チームマネジメン:方向性を示してゴールを目指すチームを作る
メンバー1人1人の力を最大限に生かして、チーム力を100%以上に引き上げるのがリーダーの役割です。
そしてそのためには、個の力を見極めて成果を最大化する戦略を立て、それらをメンバーに共有し、リーダー自ら陣頭指揮を取っていくチームマネジメントが必要です。
ここからはそのようなチームマネジメントを行う方法について解説していきます。
チームビジョンを語り助け合うチームをつくる
チーム力を高める上で重要になるのは、メンバーに「このチームのために頑張りたい」と思ってもらうことです。
メンバー全員に協力意識と連帯感があれば、そのチーム力は何倍にもふくれ上がります。
では、そのためにリーダーは何をすれば良いのでしょうか?
それは、「チームの目標とビジョンをメンバーに共有すること」です。
一般的に、ビジョンとは「将来のあるべき姿」、目標とは「そのビジョンを達成するための中間地点」を言います。
たとえば、チームで商品Aの立ち上げを行っているとすれば、
チームビジョンは、商品Aでお客様の困りごとを解決させること。そしてその目標は、商品Aを30個販売することなどがあげられます。
このようなビジョンと目標は、メンバーのやりがいとモチベーションになります。
そして、全員と共有することでチームの団結力が高まります。
なぜなら、一人だけがうまくいくことに意味がなく、チームとして成功しなくては意味がないという考え方がチーム内で生まれるからです。
丁寧な対応を心がける
リーダーになると日々のタスクに追われ余裕がなくなってしまうあまり、メンバーへの対応が雑になってしまうことがあります。
しかしどんなにリーダーが忙しくても、「今いいですか?」とメンバーから聞かれたら、「今忙しいから後にして」と断ってはいけません。
なぜなら、次からメンバーが相談しにくくなってしまい、チームでコミュニケーションが取りにくくなってしまうからです。
リーダーは必ず今やっている作業を中断してでも、メンバーとのコミュニケーションを最優先する必要があります。
この際のポイントは、作業の手を止めてメンバーの目を見て返事することです。パソコンの画面を見ながら返事をしたのではメンバーが委縮してしまいます。
また、メンバーからの連絡を後にするのもよろしくありません。
メンバーは、リーダーにせっかく「ホウレンソウ」を行ったのに、そのリアクションがなければそのコミュニケーション自体が薄れていくからです。
今では電話以外にメールやチャットもビジネスコミュニケーションとして主流になっています。
連絡はしやすくなる一方で、それを処理する量が増えるためリーダーはすべての返事をタイムリーに見ることは難しいかと思います。
したがって、メンバーへの返信は24時間以内に。
忙しいときには「イイね」や「了解」だけでも十分です。
メンバーにとっては、リーダーが読んで反応してくれたということに大きな意味があるからです。
③ビジネスマネジメント:成果を最大化する戦略を実行する

チームや組織にとってのゴールは「ビジネス目標」を達成させることです。
そして、リーダーにはそのための「金額」や「件数」などの数字が組織から課されるかと思います。
リーダーは、その目標を達成するために、リーダーシップを発揮して戦略を練り上げて「ビジネス成果を最大化する」ことを徹底的に行う必要があります。
繰り返しになりますが、ビジネスは成果=数字が命です。
ここでは、そのビジネス戦略を考えるうえで大切なポイントについて解説します。
パレートの法則とロングテール戦略を使いこなす
ビジネスを行ううえで「メリハリ」という考え方は重要です。
なぜなら、会社のヒトモノカネなどの原資は限られているため、すべてのリソースをビジネスに投下できるわけではないからです。
リーダーは、限られた原資を使って最大限の成果を上げるにはどうすべきかの戦略を考えて実行する必要があります。
ビジネス戦略を立てるうえで有効な考え方として、イタリアの経済学者が提唱した「パレートの法則」があります。
パレートの法則
・売上の8割は、2割の上顧客が占めている
・会社の利益の8割は、全従業員のうち2割が生み出している
・2割の富裕者層が、納税額の8割を担っている
・トラブルの8割は、全システムのうちの2割に原因がある
・20%の従業員が、成果の80%を生み出している
引用:リーダー1年目のマネジメント大全 P205
成果分布の法則で「20:80の法則」や「2:8の法則」とも呼ばれています。
この法則はビジネスの様々な考え方に当てはめることができます。
たとえば「メンバーへのタスクの振り方」です。
パレートの法則によれば、チームの仕事すべてを全力でやろうとするのは非効率だということが分かります。
なぜなら仕事には「2割の重要な仕事」と「8割の重要でない仕事」に分かれているからです。
そのため「2割の重要な仕事」を「チーム内で20%の優秀なメンバー」にタスクを割り振ることで効率化することができます。
しかし、ここまで極端なアサインはビジネス上で行いにくいため、状況に合わせてパレートの法則を考慮し効果的な戦略を考えていくことが有効です。
一方で、8割を活用する「ロングテール戦略」という考え方もビジネスにあります。
恐竜のしっぽにたとえてロングテールと呼ばれているようです。
ロングテール戦略とは、上位20%を占める売れる商品でなくても、残り80%を積み上げていくと20%に匹敵するという考え方で、インターネットビジネスの拡大の影響で有効になった戦略と言われています。
80%だからと言ってあっさり切り捨てるのではなく、一つひとつが小さい80%を積み上げていくこともビジネス上では強みや個性になることも覚えておきましょう。
④セルフマネジメント:自分自身を高めることも忘れない
リーダーは、メンバーだけでなくリーダーである自分自身も磨き続けていくことが大切です。
なぜならリーダーは、キャリアやスキルを大きく伸ばすチャンスのある役割だからです。
メンバーをマネジメントするのと並行して、自分自身をマネジメントしていく。
本記事の最後には、新任リーダーとして己を高めるために忘れてはいけないことについて解説していきます。
リーダーの仕事は選択と集中で行う
リーダーに選ばれたということは、組織やメンバーを預かる立場になるということです。
そして会社は、それができる資質のある人にリーダーを任せます。
しかし、リーダーに選ばれたからと言って、それがゴールにはなりません。
ここがキャリアにおいての第一歩に過ぎないのです。
上司や先輩は、あなたが今よりも大きな組織でリーダーが務まるかどうかを今の仕事ぶりから見ています。
そして、それは主に3つのポイントで判断しています。
- ビジネスで成果が出せるか
- 組織をマネジメントできるか
- 人材育成できるか
リーダーがやるべきタスクは実にたくさんあります。
しかし上記の3つ、特に組織の成果が出せていなければ、いかにタスクをこなせてもリーダーとして評価はされません。
そこでリーダーは、本記事でご紹介した内容ができるようになってきましたら、
次からは自分のタスクの一部をメンバーに振って、自分の仕事のバランスを取るようにしましょう。
繰り返しになりますが、ビジネスは数字が命です。
組織の成果を出すために、自分の仕事に優先順位をつけてやるべきことは徹底的にやりきるようにしましょう。
このような自分のタスクにメリハリをつけて成果にコミットし続けて、今いるチーム以上の成果を引き出す能力が自分にはあることを周りにアピールしましょう。
本書を読んだ感想
2ヶ月前に読んだ本でアウトプットが遅くなりましたが、私にはかなりの良書でした。
まずは圧倒的な読みやすさです。
各章の構成がハッキリしているうえに各節は事例を使った説明が多く、「あー、確かに」と読んでて納得することが多かったです。
また大全なだけあって、紹介事例の多さもgoodなポイントでした。
新任リーダーでしたらこの本を初めに読んでおけば、これからぶつかる壁やすべき事を事前に把握できるので、リーダーへの抵抗感が少し和らぐのではないでしょうか。
しかし、一つひとつの事例の深掘りは薄いので「マネジメントも本格的にも学びたい」と思っているリーダー層の方には、少し物足りない内容なのかなとも思いました。
とは言え、新任リーダーの方には間違いなしの良書ですので、是非読んでみてください。
最後までお読みいただき、ありがとうございました。
これからもブログの記事向上に向けて投稿を続けていきます。
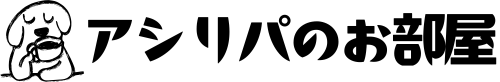
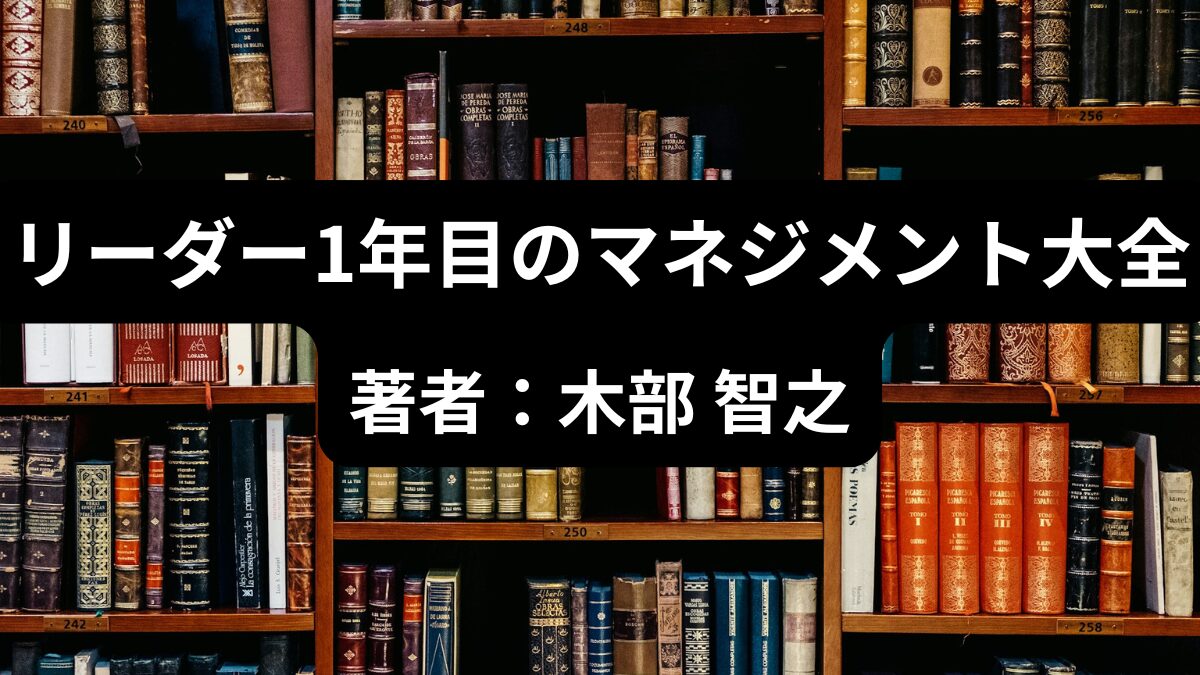


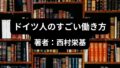
コメント