こんにちは、アシリパです。
ジョージ・オーウェル著書の「本 vs 煙草 」を読みました。
キャッチ―なタイトルですがその中身は、「読書と娯楽にかけた費用を比較して読書の価値を考えさせる」といった興味深い内容になっています。
執筆されたのは第二次世界大戦直後のイギリスです。
当時ジリ貧だったイギリスでは、高いお金で本を買うよりも、酒や煙草などの娯楽を優先するのが当たり前の風景でした。
しかしそこで著者は、「読書は本当にお金のかかるものなのか?」と考えます。
そして著者自身が読書と酒や煙草に使う費用の比較を行ったのです。
この本が面白いのは、読書と酒、煙草などの娯楽の価値をお金を使って比較したところでしょうか。
読書離れが進み、SNS、サブスク、ネットゲームなどの娯楽があふれた時代を生きる私たちにとっても、このテーマは興味深いものになるかと思います。
「昔も今も読書は娯楽よりも費用がかかるなのか?」
本記事では、私の読書に対する想いも入れながら解説していきたいと思います。
作品情報
本 vs 煙草
著者:ジョージ・オーウェル
この本は「5分文庫シリーズ」として出版されています。
「5分で本当に本が読めるのか?」と思ってしまいますが、いざ読み始めるとユーモアあふれる内容と訳者の解説で一気にひきこまれます。当時のお金の価値や著者が生きた時代については理解しにくい箇所がありますが、注釈が充実してますので安心して読み進めることができます。
昔の読書と娯楽にかかる費用

まず著者は、これまで購入した本や新聞などの定期刊行物、図書館の会費などから読み物に使ったすべての費用を算出しようとします。
それが165ポンド15シリング、円換算だと「994,500円」で、年間だと25ポンド、円換算だと「150,000円」でした。
次に、著者は年間の煙草とビールに費やす費用を割り出します。
すると、年間で20ポンドほどになりました。
本25ポンド > 娯楽20ポンド
読書よりも娯楽の方が費用が安かったわけですが、当時の物価やイギリス国民の平均値なども考慮すると、娯楽にかかる費用は年間40ポンドであることが判明します。
そして、この数値は毎日煙草を1箱と週に6回生ビールをグラスで飲むことができる費用と同等のようです。
娯楽40ポンド > 本25ポンド
こう見ると読書は決してお金がかかる趣味ではないことが分かります。
むしろ著者は、1時間あたりの娯楽費にたとえるなら映画館の高級な席代と同じ位でしかないと言います。
そして本書の最後に、「別に本の値段が高いわけでなく、多くの人にとって読書はドッグレースや映画、飲み歩きほど刺激的な趣味ではない」と締めくくります。
著者の思う読書の価値
本書のなかで著者は、「娯楽よりも読書の方が優れている」とは決して言いません。
むしろ「自分は娯楽にこんだけ使っているよー」と、どちらかと言うと娯楽に肯定的です。
著者が思う読書観について直接的な言及はないわけですが、それっぽいことが書かれた箇所はいくつか見つかります。
- 本の価格と、それを読むことで得られる価値の関係を語るのは難しい
- 心に深く根付き人生観を変えてしまう本、読み始めたものの途中で放り出してしまう本もみんな同じ価格かもしれない
読書の価値はお金で単純に図ることができず、1人1人の考え方や向き合い方が違うそうです。
たしかに読書を「娯楽」とみなすか「学び」とみなすかで、読書の価値は大きく変わってきます。
今の読書と娯楽にかかる費用
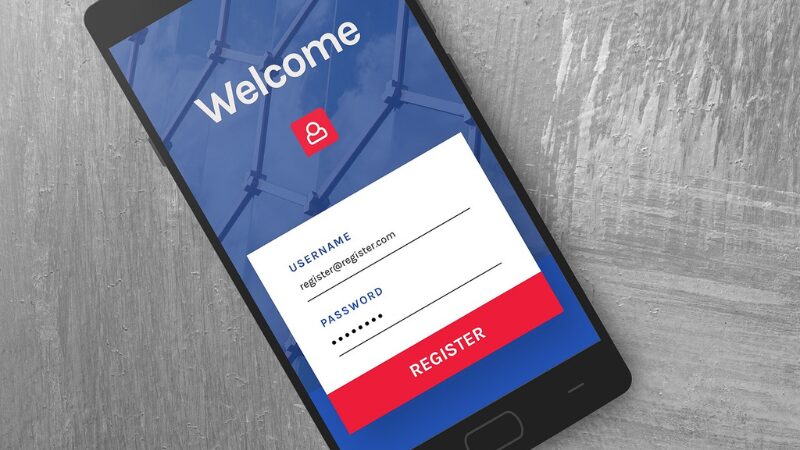
読書と娯楽の費用をお金で比較すると、当時は娯楽費の方が圧倒的に高かったです。
では現代はどうでしょうか?
ここからは現代のデータを使って比較していきたいと思います。
文化庁の2024年調査データによると、毎月読書を行っている人の1カ月の読書量は「平均1冊以上」となっています。
年間にすると、12冊程度です。
ただし、毎月読書を行っている人の割合は全体の36.9%で、そもそも読まない人の割合は全体の約6割を占めているそうです。
※参考:文化庁 令和5年度「国語に関する世論調査」の結果の概要
一方で2024年の書籍市場は、電子書籍が「5,660億円」、書籍が「5,937億円」で、合計「11,597億円」になるそうです。
※参考:出版科学研究所 日本の出版販売額
2024年の日本の人口が1,24億人だとすると、一人あたりの年間書籍代平均は「9,352円」になります。
つまり、一人当たりの1カ月の書籍代は平均で「779円」です。
文化庁のデータでは、月に7冊以上読むというデータもあったため、これを考えると読書量が多い人の年間の書籍代は「65,436円」になります。
そしてここからは、煙草とお酒にかかる費用を見ていきます。
まずは煙草からです。
こちらの記事を参考にさせていただくと、毎月の煙草代の平均は「9,247円」で、年換算すると「110,964円」になります。
※参考:イオン銀行 タマルWeb
次にお酒です。
こちらの記事を参考にさせていただくと、2人以上世帯の年間の酒代は「47,500円」になります。
※参考:ファイナンシャルシールド
これを年間のコストで順位付けしてみると次のようになります。
読書量が平均の人:娯楽158,464円 > 書籍9,352円
読書量が多い人:娯楽158,464円 > 書籍65,436円
昔と今も読書は娯楽より費用が高いわけではありませんでした。
しかし昔と明らかに違うのは、読書をしない人の数が増えているということです。
はじめに言いましたが、2024年では全体の6割の人が読書をしないそうです。
これは、6年前と比べて約20%も増えている割合です。
つまり、著者が言うように現代人にとっても読書は刺激的な趣味ではなく、むしろその考え方は強まっているように思えます。
「可処分時間」という考え方

巻末で訳者が「現代は可処分時間が減っている」と話していました。
可処分時間とは、仕事や通勤や家事、睡眠などの必要最低限の時間を差し引いた際の「個人が1日に使える自由時間」のことを言います。
現代における一人当たりの可処分時間は約6時間程度と言われていますが、少なすぎる感は否めません。
SNSやネット動画などのサブスクサービスが普及した今では、昔と比べると可処分時間の奪い合いが激しくなっているのが容易に想像できると思います。
無料ですぐに視聴でき、しかも面白いコンテンツが充実しているネットサービスと、お金がかかり、しかも内容は当たりはずれがある本とでは、可処分時間をネットサービスにあてたくなるのは当然の心理だと思います。
読書のメリット👍・デメリット👎

私は読書歴20年で「読書を全国民の共通の趣味にしたい」と思っている読書絶対信者の中の一人です。
たしかに読書は、勝手に面白いコンテンツが流れてくるネットサービスと違って、自分からしようと思わなければしないものです。
どちらかというと、娯楽要素よりも「学び」の要素が強いわけです。
しかし、その能動的に行う趣味だからこそ多くのメリットがあります。
ここからは、そんな私が思う読書のメリット・デメリットについて改めて考えたいと思います。
👍学びのコスパ
まずは学びの手軽さではないでしょうか。
読書は、時間や場所にとらわれずに少ない費用で行うことができる「学び」の唯一の手段です。
学びには、スクールやセミナーに通う方法などが考えられますが、読書ほどコスパに優れているわけではありません。
本来なら高い授業料を払わなければ学ぶことができない有名な専門家や先生、歴史上の偉人から、高度な知識や教養を学ぶことができます。
しかもたった数千円の費用でです。
この圧倒的なコスパは本の一番の強みだと思います。
また、本は携帯性に優れています。
持ち運びしやすい丁度よい大きさですので、時間や場所を気にせず読書ができてしまうのもポイントの1つです。
👍情報量の多さ
学びの手段にネットや動画も考えられますが、情報量の多さでは本に及びません。
一般的な本のページ数はだいたい200~300ページで、文字数にするとおよそ10万字ほどだと言われています。
それを読むとなるとかなりの時間がかかってしまいますが、本特有の情報量は私たちに幅広い知識と教養を与えます。
一方で、ネットや動画は検索性の高さと情報を端的に伝えるのを得意としています。
素早く必要最低限の情報を探すことが目的であれば、ネットや動画は最適です。
しかし、何かのジャンルを学ぶとなれば、本に書かれた情報を体系的に網羅的に吸収する方が適しています。
👍考える習慣がつく

本を読んでいると、ある文章で立ち止まる瞬間があります。
たとえば、その内容に共感したときや、新たな学びがあったときです。
また、その文章の意味が分からない瞬間などでも立ち止まって読み返すことがあるかと思います。
その瞬間に脳の中では、書かれた内容を自分が分かるようにかみ砕いて理解しようと活発化します。
つまり、言語化して自分の言葉に置き換えようと脳がフル回転している状態です。
一方で、動画を見ている瞬間は読書している時ほど脳は回転していません。
なぜなら、私たちに違和感で立ち止まらせて自分の言葉で言語化する時間を与えないからです。
動画は情報を一方的に伝達させますが、読書は自分から能動的に情報を読み取りにいかなければなりません。
立ち止まって思考する時間がある読書と、その時間を与えずに情報を流し続ける動画では、どちらを選択するかで思考する回数やその時間量が大きく変わってくるはずです。
思考力は生きていくために重要な力です。
人間に必要な力となる思考力を読書で鍛えることができるなら動画よりも読書を優先すべきかと思います。
👍リラックス効果
読書にはリラックス効果があると言われています。
ある論文では「たった6分間の読書でストレスを68%も減少させた」、「読書習慣がある人は、ない人に比べると死亡リスクが17%も低かった」などのエビデンスも出ています。
たしかに読書をするとその本の中身に没頭してしまって、周りのことなど気にならない瞬間が訪れます。
それは映画や漫画を観ている感覚に少し似ていて、「次はどうなるのだろう」と心の中でドキドキ・ワクワクしている状態です。
つまり、周りのことなど気にせず今に集中できている状態です。
そこにはストレスの原因となる雑念などは一切出てきません。
ストレスがかからないことで高いリラックス効果を受けている状態です。
さらに読書は映画や漫画と違って、「新しい知識を得る」ことにドキドキ・ワクワクしている状態ですので脳にとっても良い刺激になります。
👎時間がかかる
読書にはたくさんのメリットがありますが、デメリットもあります。
その一つに、本を読むのにある程度の時間がかかってしまうということです。
ジャンルにもよりますが、一般的なビジネス書籍を読むとなると少なくとも1〜2時間はかかってしまいます。
ただでさえ可処分時間が少ない現代において、1~2時間はとても大きな数字です。
ちまたでは読書の速読法などが紹介されてますが、それを身に着けるまでにもかなりの時間が必要になってしまいます。
👎コストがかかる
一昔前と比べると無料で読める書籍が増えてきましたが、新しく発売された本を読もうと思ったら一冊に千円〜二千円ほどかかってしまいます。
一冊二千円の本を仮に2時間で読み終えたとすると、1時間あたり千円を消費している計算になります。
これが高いか低いかは人それぞれですが、それが良い本でなければ「もったいない買い物であった」と誰しもが思ってしまうのではないでしょうか。
電子書籍のススメ
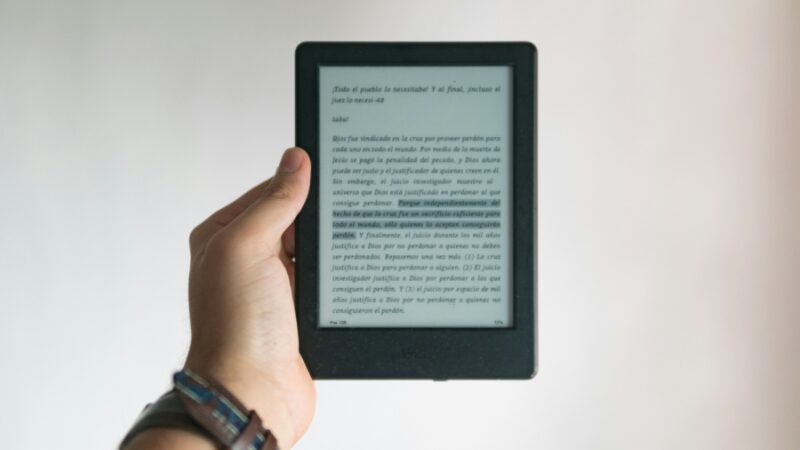
読書にはメリットとデメリットがありますが、今は昔に比べるとデメリットが少し和らいだと感じています。
なぜなら電子書籍や電子書籍リーダーが普及してきたからです。
電子書籍は、紙の本のデメリットをうまく対処しています。
たとえばコストです。
電子書籍は紙の本より若干安く購入できる傾向にあります。
Amazonなどの電子書籍を取り扱うWebサイトがセールやキャンペーンを定期的に行っているからです。
実際に、定価の5%~10%値引きで購入できるのは珍しくありません。
また、Amazonプライムの会員であれば無料でいくつかの電子書籍を読むことができます。
今ではそのジャンル数が多くなっているため、たくさんの本を無料で読み漁ることができます。
さらに電子書籍リーダーを活用すれば読書の幅が広がります。
電子書籍リーダーは、電子書籍を端末上にダウンロードできる端末です。
その数は本にすると約数千冊です。
また、端末にはブルーライトカット機能や、マーカー機能、付箋入れなどのリアル本では得られない便利な機能がついています。
私は普段の読書にKindle Paperwhiteを活用していますが、満足度が高いと実感しています。
紙の使い勝手は踏襲してますし、デバイス自体が本の大きさと同じくらいのサイズ感になっていますので読書のしにくさは一切ありません。
読書したくなったらこれを持ち出せば瞬時に読書を楽しむことができます。
紙の本や読書するのに抵抗感をお持ちでしたら、一度試してみるのをおススメします。
読書の価値が低下している現代だからこそ、便利なツールを活用して読書の心理的なハードルを下げることが大切かと思います。
最後までお読みいただき、ありがとうございました。
これからもブログの記事向上に向けて投稿を続けていきます。
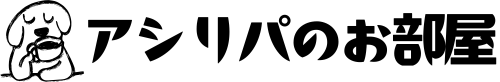
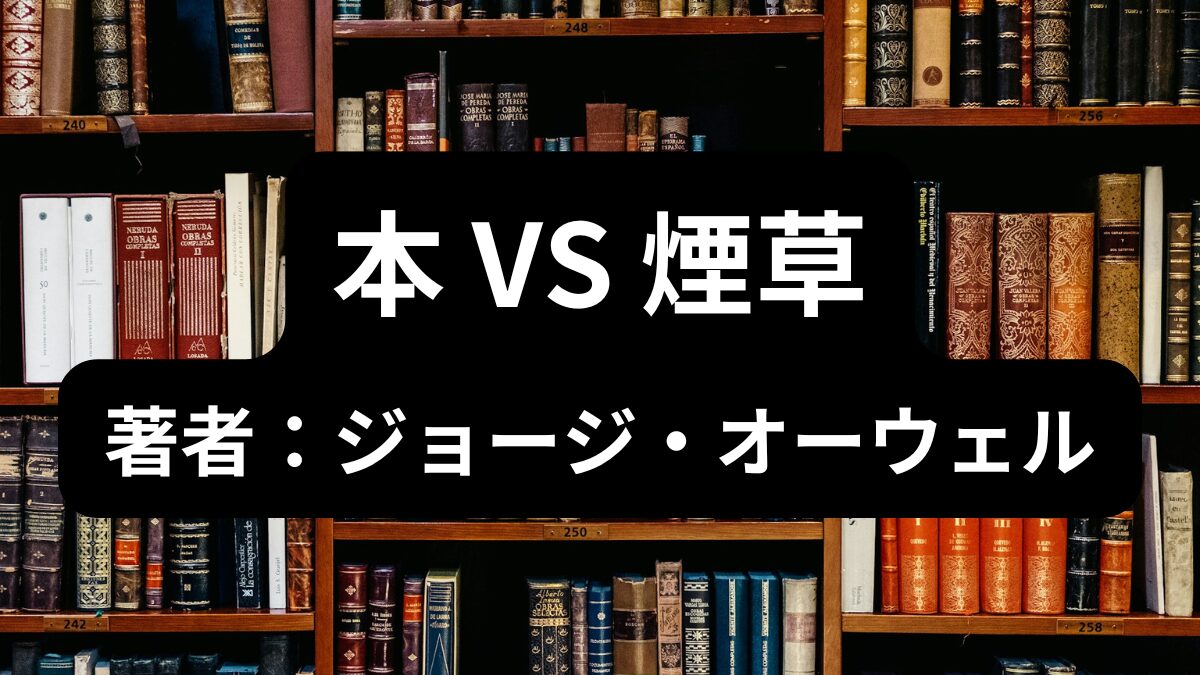

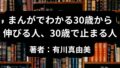
コメント