こんにちは、アシリパです。
毎日お仕事に追われて心に余裕がなくなっていませんか?
もっと効率的に仕事ができたらプライベートが充実するのにと思っていませんか?
実はそのお悩みを解決するヒントは、ドイツ人の働き方にあるんです。
たとえばドイツ人の働き方には、次の特徴があります。
- 朝早くから働き始めて夕方には仕事を終える
- 終業間際に一斉にディスクを片付け始めて、17時にはオフィスに人がいない
- 年間約30日間の有給休暇をフル取得
- 2~3週間の長期休暇は当たり前にもかかわらず仕事は回る
引用:ドイツ人のすごい働き方 P5
日本企業では考えられない働き方ですが、それがドイツ人の高い労働生産性を実現させています。
そして実際のデータでも、ドイツ人の高い労働生産性は証明されています。
- GDPは日本を抜いて世界第3位(2023年)
- 日本より年間266時間短い労働時間(2022年)
- 日本より約40%多い平均賃金(ドル換算・2022年)
引用:ドイツ人のすごい働き方 P6
「日本人は働き過ぎ!」とよく言われますが、それでもドイツ人の労働生産性の高さに驚くデータかと思います。
そこで今回は、「お仕事が終わらない!と毎日悩んでいる方」におススメしたい一冊をご紹介します。
その本の中から特に「今すぐ実践できるドイツ式働き方の取り入れ方」について本記事で解説します。
これを実践できれば、お仕事のストレスから解放されるきっかけになるだけでなく、労働生産性のアップにもつながるかと思います。
それでは、さっそく見ていきましょう。
今すぐにドイツ式働き方が知りたい方は、こちらからどうぞ!
作品情報
ドイツ人のすごい働き方
著者:西村栄基
ドイツ企業で働く現役会社員さんが書かれた本です。
日本企業でも働いた経験をお持ちですので、ドイツ人と日本人の働き方の違いについて事例をあげながら具体的に解説しています。
文章表現が易しく、文字数が多くないため本を読むのが苦手な方でも読み易い一冊だと思います。
また各章・各節の最後では重要なところのまとめもありますので、振り返りし易いのもgoodなポイントですね。
ドイツ企業の日常

ドイツ式を取り入れた日本人の働き方を解説する前に、ドイツ人が普段どのような働き方をしているのかについてまずは見ていきたいと思います。
ドイツ人の朝は早い
ドイツでは朝早くから働き、夕方には帰宅するのが一般的です。
早い人であれば7時前から出勤して、午後3時頃には一日の業務を終える、なんてこともあるようです。
なぜなら、ドイツ人は仕事とプライベートのバランスを大事にしているからです。
プライベートの時間を取るには、労働時間内に仕事を完結させるという考え方が一般的とされています。
そのため、ほとんどの企業はフレックスタイム制を導入してますので、出勤時間は自由です。
週に38.5~40時間の労働時間で残業は一切せずに、朝の集中できる時間帯を活用して、その日の仕事はその日に終わらせるようにします。
時間は決して無駄にしない
日本で多く目にする非生産的な会議も、ドイツでは一切の無駄がありません。
ドイツでは、会議で発言しない人は必要とされません。
参加者全員が自分の意見を用意して、発言する文化が根付いています。
会議に参加する必要がないのなら、一人でゴリゴリと仕事をする割り切り方もあるそうです。
また、会議内の議事録にも一切の無駄がありません。
事前に議事録のテンプレートを用意して、会議中の合間に議事録を作成します。
会議の中で決めたアクションアイテムは、会議の最後に参加者から合意を取り、会議が終われば内容をチェックし、その日のうちに「速報版の議事録」を発行します。
日本では会議の後に思い出しながら作る議事録を、ドイツでは効率的に仕上げて全員と共有するにはどうすれば良いのかを考え実行しています。
働く環境にこだわる
ドイツのオフィス環境は日本と違ってこだわりがあります。
まずはカフェスペースです。
ドイツでは、オフィスの一か所にソフトドリンクやミネラルウォーターが入った冷蔵庫やエスプレッソマシーンが置かれたカフェエリアがあります。
朝早く出社したドイツ人は、まずそこに集まりコーヒーを飲むのが習慣です。
そして、ここでは上司部下関係なくフリーでフラットな環境です。
カフェタイムを楽しみながら「週末何をしていたのか」などのプライベートの話題から始まり、「プロジェクトの進捗はどうか」などの仕事の話へと徐々にシフトしていきます。
このように、ドイツではプライベートから仕事へ脳を切り替えるためにカフェスペースが設けられてますし、出社したらほとんどの社員がそこでの一服を楽しむことが習慣化されています。
また、ドイツのオフィスは広々とした開放的な作りになっています。
ドイツでは作業スペースの広さと思考の広さは比例すると考えがあるため、個人の席は2つのデスクが組み合わさっており、大きな作業スペースが各自に用意されています。
また、フロアは仕切りで区切らずに隣席との距離は2メートル以上離すことでプライベートな空間を確保しています。
フロア内には、観葉植物がたくさん置かれていますので開放的な空間と相まって、クリーンなオフィスの雰囲気になっています。
この空間があるからこそ、一人一人が集中して効率的に仕事に向き合うことができるのです。
ドイツ人の働き方が生まれた背景

ここでは、高い労働生産性を生むドイツ人の働き方が生まれた背景について解説します。
ドイツ人の効率的な働き方の背景には、文化・歴史・民族的な要因があります。
長期休暇を軸とした働き方
ドイツの企業では年間で30日間の有給休暇が与えられます。
完全週休2日制で祝日を加えると、年間では110日程度の休みがあるため、有給休暇と合わせるとドイツ人は年間140日も休んでいることになります。
年に4割近く休むドイツ人は、長期休暇を取得するのが一般的です。
夏休みは3週連続や長くて1カ月休む人もいるようです。
このように、長期休暇が普及した背景には、「連邦休暇法」の施行と「旅行会社の活躍」があります。
1963年に施行された「連邦休暇法」とは、週6日フルタイムは最低24日間、週5日の場合は年間20日間の有給休暇が与えられるものです。
日本人と違って「個人主義」の意識が根強いドイツ人は、有給休暇は労働者の当然の権利で「とらなければいけないもの」と考えています。
「連邦休暇法」が施行されることで、長期休暇が取得しやすくなったのです。
また当時、国内にあった旅行会社の「ネッカーマン」は、格安でバカンスを提供することをキャッチコピーに国内に広まったことで、「長期休暇は家族で旅行に行くもの」というライフスタイルが定着しました。
つまり、長期休暇が取れる法が整備されて、休暇を取ることが当然の権利だと労働者に広まり、その手段として旅行が定着したというわけです。
企業でもそれは当たり前の文化ですので、それを考慮して仕事が進むようオペレーションが組まれています。
仕事とプライベートのバランス意識
ドイツ人は休むときはとことん休みます。
一方で仕事をするときは決められた時間内できっちりと仕事をこなします。
このように、仕事と休みのメリハリがドイツの高い労働生産性につながっているのです。
ドイツ人はまずは新年が明けたら「今年はいつ休むか」の計画を立てて仕事を入れない日をまず確保します。
早々に休暇計画を立てることで、日常的な仕事のモチベーションにつなげてるのです。
ドイツ人は実際の長期休暇では、「空っぽ」になることに注力します。
つまり、何も考えなくて良い場所で長期休暇を過ごすことが多いのです。
たとえばドイツ人に人気のリゾート地であるマヨルカ島、カナリア諸島、コスタ・デル・ソルではオールインクルーシブのホテルが人気です。
食事はビュッフェスタイルで3食提供され飲み物もホテル代に含まれるオールインクルーシブでは、「今日の食事をどうするか」というレストラン選びから開放されます。
そして日中はビーチサイドでひたすら寝そべって過ごします。
このように、何もしないスタイルは、心と体を仕事のストレスや責任から完全に開放してエネルギーを充填する、いわばマインドフルネスの状態です。
もちろん会社は本人が長期休暇中は一切連絡をしません。
こうして長期休暇を利用し、とことん仕事のことを考えずマインドフルネスの状態で過ごすことで、仕事復帰の際はメリハリをもって働くことができるのです。
プロフェッショナルを育てる社会制度
日本と違って、ドイツでは入社後に即戦力として働くことができるような仕組みができあがっています。
たとえば、就職する年齢です。
日本では大学を卒業してからすぐに入社し働くことが一般的ですが、ドイツでは大学を卒業しただけでは仕事に就くことはできず、専門学校に通ったり、企業のトレーニングプログラムを受けたり、大学院で学びなおしたりします。
そのためドイツ人が正社員として働きはじめるのは平均30歳前後と言われています。
また、ドイツの雇用形態も日本と異なっています。
ドイツでは「ジョブ型雇用制度」を導入しており、1つの分野のプロフェッショナルとして雇用されることが雇用の条件となっています。
さらに、職業学校での理論教育と職場での実務訓練を同時に行う「デュアルシステム」の採用や、継続的なキャリアのために最新技術やスキルを習得するための「リスキリング」という学びなおしという文化も普及しています。
このようにドイツ人はプロフェッショナルとして働くことで高い生産性を上げていますし、そのための仕組みが国内で出来上がっています。
「自分は何の専門家になるのか?」
ドイツではこの選択を基礎教育が終わった10歳前後のタイミングで迫られます。
ドイツ人は、日本の小学校と同様に6歳から10歳の間にグルンドジューレという基礎教育を受けますが、そのあとは大きく3つの選択肢が与えられます。
| ー | ギムナジウム | レアルシューレ | ハプトシューレ |
|---|---|---|---|
| 目的 | 大学進学に向けた準備 | 実践的な学問と職業に関する教育 | 実務的なスキルと基本的な教育 |
| 期間 | 基礎学校から数えて5年生から、12年生または13年生まで | 基礎学校から数えて5年生から10年生まで | 基礎学校から数えて5年生から9年生、または10年生まで |
| 内容 | 言語、数学、人文学などカリキュラムは多岐にわたる。修了後は大学への入学資格を与えられる | 実用的なスキルや職業訓練への導入。修了後は特定の専門学校や職業訓練校への進学が可能 | 職業訓練がメイン。修了すると職業訓練校や特定の専門職への道が開かれる |
| 日本でいうと | 中高一貫の進学校 | 工業・商業高校 | 専門学校 |
このような自分の強みや適正を探す国としての仕組みは、ドイツ人全員をプロフェッショナルに育てることにつながっています。
しかし一方で、教育機会の不平等も生むということで最近ではゲザムトシューレという3つの進路の特徴を合わせた総合学校という第4の選択肢が出てきているようです。
オススメのワイブリットワーク

ここまではドイツの高い労働生産を実現する現状とその背景について解説しました。
国の仕組みとして根付いているところもありますが、私たちの働き方やライフスタイルの参考にできるところもたくさんあります。
そこでここからは、今すぐ実践できるドイツ式を取り入れた働き方についておススメなものを解説していきます。
ドイツ流早起き習慣
ドイツ人は朝早くに起きて仕事に取り掛かることで、仕事を早く終わらせて夕方からは家族の時間や副業にあてています。
私たち日本人も早起きの習慣を作ることができれば、余暇時間を増やしたり、頭が冴えてる朝の時間を有効活用させて人生をより良い活動にあてることができます。
しかし、いきなり早起きの習慣化は難しいですし、無理に行えば仕事にまで支障が出てしまいます。
そこで、本書では無理なく早起きを習慣化させる方法として3つを紹介しています。
- 15分早起きチャレンジ
- 14時以降のカフェインカット
- 起床後ルーティンの自動化
①15分早起きチャレンジ
早起きできるように徐々に体を慣らしていく方法です。
たとえばこれまで7時に起きていたとしたら、1週間ごとに15分ずつ起床時間を早めていきます。
1週目は6時45分起床、2週目は6時半30分起床と段階的に進めていくと体は自然と早起きに慣れていきます。
そして何よりたった15分のゆとりが生まれることで早起きのありがたさに気づき習慣化へのモチベーションにつながるのです。
②14時以降のカフェインカット
寝る前にカフェインを取ると眠れなくなるのは当たり前のことですが、カフェインを摂取する時間を気にするのも早起きの習慣化には大切です。
一般的にカフェインは摂取から約5〜6時間の効き目があると言われています。
人によって体質は異なるため良質な就寝を取ると考えると眠る8時間前には摂取を控えたいところ。朝6時に起床をすると考えて8時間睡眠を確保して22時に眠るとするならば、就寝する8時間前のカフェイン摂取は14時までにすると良いです。
③起床後ルーティンの自動化
せっかく早起きしてもベットでそのままスマホをいじっていたら貴重な時間があっという間にすぎてしまいますし、早起きのありがたみが薄れて、もとの生活に戻りかねません。
早起きして心と時間の余裕を手に入れる。そのためには起床後にやるべきことを明確化させて無駄なことをしないようなルーティンを作りあげることが大切です。
また「読書する」「瞑想する」「運動する」など、やるべきことはなんでも良いですが中長期的な目標をセットにしてルーティン化するのがオススメです。
「副業の知識をつけたいから読書する」「次にマラソン大会に参加するから運動する」などの目標を合わせることで、早起きのルーティンが乱れることなくモチベーションを維持し続けることができます。
無駄を省いて効率化できる会議&時間設定
目的意識がハッキリしていて効率化意識があればダラダラと働くことがなくなります。
ドイツ人の働き方のすべてをマネできれば労働生産性は劇的に変わりそうですが、会社全体の仕組みを変える必要があるため現実的に難しそうです。
そこでここではドイツ人の考え方にならった無駄の省き方について具体例を2つ紹介します。
- ムダな会議のふるい分け
- 時間設定の有効活用
①ムダな会議のふるい分け
ドイツ人は「自分が発言する機会がない会議」には参加しないのが一般的ですし、ムダな会議はしないことが推奨されています。
日本人も同じような考え方ができればムダな会議をなくせるはずですが、いざ会議をなくす提案を職場にするとなると気が引けてしまいます。
そこで、提案をしやすくするために「会議の棚卸し」を行い、会議をなくす理由をロジカルに説明できるようにします。
会議の棚卸しを行うさいに考えたいポイントは次の通りです。
Q「この会議のアジェンダは、意思決定(議論)・報告・情報共有のいずれか?」
Q「意思決定(議論)なのであれば、それへ自分はどのような価値を提供できるのか?」
Q「価値を提供できたとして、発言の機会はあり、意思決定(議論)に影響するののか?」
引用:ドイツ人のすごい働き方 P96
会議の内容が情報共有や報告であれば、議事録を見さえすれば良いです。
一方で意思決定が目的であれば、自分はそれに影響力があるかを考えます。
たとえば影響を与えるだけの権限や専門性、見解を自分が持っているかどうかです。
極端な話し、それがなければ会議に出る必要がないと思って会議に参加しないのも一つの方法です。
②時間設定の有効活用
ドイツ人は仕事とプライベートの時間を明確に分けることで高い労働生産性を実現してます。
そして、これは科学的にも証明されています。
「パーキンソンの法則」と言って「仕事の量は、完成のために与えられた時間をすべて満たすまで膨張する」という科学的な法則があります。
たとえば指定納期よりも早く資料ができあがったら細かい箇所を期日ギリギリまで修正してしまうような行動を人間は行ってしまうということです。
しかし、これを逆に考えると「完成のための時間を限定すれば、仕事の量はその中に収束する」とも言えます。
ドイツ人の働き方のように、仕事の時間をハッキリさせる仕組みがあれば仕事の効率性は上がるはずです。
たとえば「ポモドーロ・テクニック」です。
作業と休憩を短いサイクルで交互に回す時間管理術ですが、やり方はいたってシンプルです。
- タイマーを25分にセットする
- タイマーがなったら5分の短い休憩をとる
ダラダラと仕事をするのではなく、仕事と休憩の時間にメリハリを出すことで作業効率は上がるはずです。
ストレスが生まれにくい環境作り
働く環境をよりよいものにすることも、ドイツ人が高い労働生産性を実現している大切な要素です。
そしてそれらは、目の前にある物理的な環境だけでなく、頭のなかを整理していくことでもあります。
ここでは働くうえで良い環境を作るためのおススメのやり方について2つご紹介します。
- ドイツ流型付け術
- タスク整理
①ドイツ流型付け術
働きやすい環境作りは目の前の整理整頓が基本です。
ドイツ人はこの整理整頓を普段から徹底的に行っていることで、モノを探すストレスからの開放や集中力アップにつなげています。
ドイツ人の整理整頓の原則はいたってシンプルです。
「モノを置く場所を決め、使ったら元の場所に戻し、モノを増やさず、増えたら捨てる」
たとえば仕事で使う文房具やツールであれば、よく使うモノは届く範囲に、使わないモノは遠くへ、と使用頻度に応じてモノの場所をまずは決めます。
置く場所が決まったら次は、使用後は元の場所に戻すことを徹底し、習慣化させます。
また紙の書類もその一例です。
できるものはすべて電子化し、できないものは置く場所を決めてカテゴリごとにファイリングします。
こうすることで、知らない間にディスクが紙でいっぱいになることを自然と防ぐことができます。
②タスク整理
頭の中を整理することも大切です。
ドイツでは個人のデスクに小さなホワイトボードを設置することで、日常のタスク管理やアイディアの整理に役立てているそうです。
「あれもこれもやることが山積み!」と思っていても、やることを書き出すとなんてことがなかった経験はありませんか?
サッと書けるようなホワイトボードを自分のデスクにも導入して1日のタスクや関わっているプロジェクトの進捗などを書いてみましょう。
可視化することで頭のなかが整理され次にやるべきことがハッキリしてきます。
また、処理した案件も横線を引いて進捗を見えるかすると、小さな達成感が出てやる気が継続します。
小さな工夫ですが効果は抜群ですのでぜひ試してみてください。
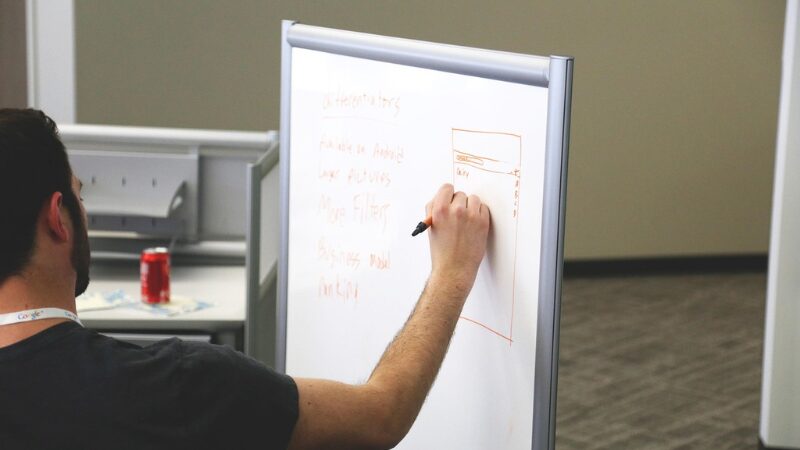
感想
ドイツは日本よりも労働生産性が高いことは以前から知っていましたが、本書を読んでその理由や実態に驚きました。なかでもドイツ人の「休日のために働いている」という仕事への価値観は衝撃的な内容でした。今でこそ日本でも自分は何のために働くのかを口に出すことは容易になってはきましたが、数年前であれば仕事を第一に考えることが当たり前でしたし、そう考えなければいけない集団心理があったかと思います。日本人がドイツ人の働き方、考え方の全てをすぐに真似ることは不可能かと思いますが、その新しい切り口はこれから日本人の私たちが仕事の価値観を作るうえで大きなヒントになるものだとも思いました。「自分は何のために働くのか」、私自身もこのテーマを定期的に振り返る時間を作っていきたいと思います。
最後までお読みいただき、ありがとうございました。
これからもブログの記事向上に向けて投稿を続けていきます。
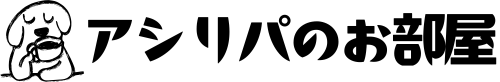
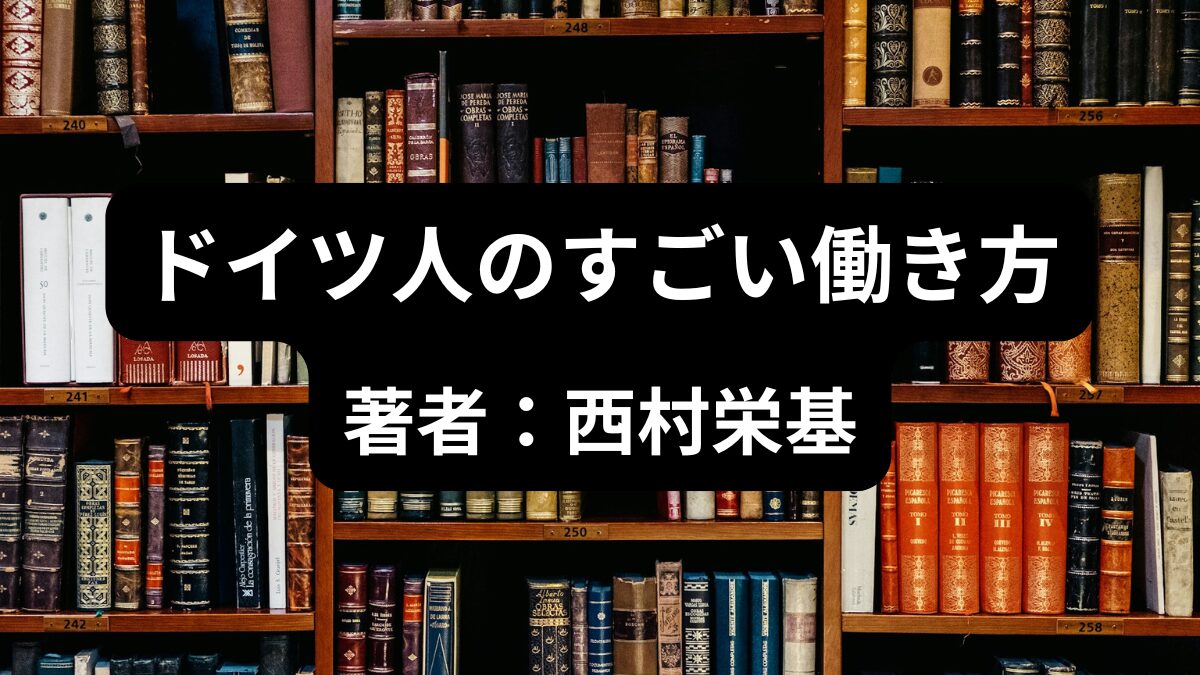

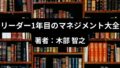

コメント