こんにちは、アシリパです。
お仕事に「心配ごと」はつきものです。
心配性さんであれば過度に心配して体調を壊してしまう
なんてことも珍しくないと思います。
そして、私もその心配性さんの1人です。
仕事中に電話がかかってくると、
「あれ、私何かしたかな?」とまず最初に不安な気持ちになります。
また、その不安や心配ごとが重なると何日も考え込んでしまい、
しまいには体調を崩すこともあります。
特に中堅の会社員になってからは、
ストレスのある仕事や複雑な人間関係で悩むことが増えて、
以前よりも心配ごとが増えてきました。
このままではいけないと思って読んだのが、今回紹介する本です。
「生活のなかで禅の教えを活かす」ことをテーマにした本ですが、
特に「仕事での活かしかた」が今の自分に刺さりました。
そこで本記事では、
「仕事での不安や悩みを軽くする禅の教え」について解説します。
同じような心境の方のお役に立てれば嬉しいです。
作品情報
心配事の9割は起こらない 減らす、手放す、忘れる「禅の教え」
著者:枡野俊明
著者は曹洞宗徳雄山建功寺の住職や、庭園デザイナーとして活躍されている禅僧です。ニューズウィーク誌の日本版で「世界が尊敬する日本人100人」にも選出されたことがある方で、国内に留まらず海外でも禅の普及に努められているようです。
なぜ禅の教えを学ぶのか

仏教の一派である禅ですが、
「禅の教え」と言われてピンとくる方は、そう多くないかと思います。
しかし、禅の教えとは私たちのとても身近なところにあって、
日々の暮らしと深い関わりがあります。
たとえば、「部屋にあがるときに脱いだ靴はきちんとそろえる」は、
誰もが一度は言われたことがある教えかと思います。
これを禅語でいうと、脚下照顧(きゃっかしょうこ)になります。
脚下照顧には、「他人を批判する前に、自分の足元を見て、言動を反省する」
という意味が込められています。
また喫茶喫飯(きっさきっぱん)という禅語は、
「お茶を飲むときはお茶を飲んで、ご飯を食べるときはご飯を食べることに集中する」
という禅語です。
そして、喫茶喫飯には、
「その当たり前を大切に丁寧に実践すれば、「今」「ここだけ」に集中でき、不安や悩みがたまらない」
という意味があります。
このように禅の教えとは、
私たちの普段の生活のなかで意味合いを持った教えなのです。
禅の教えで心を軽くすることができる

禅僧の著者は職業柄、人からの相談を受けることが多いようです。
ですが、「そのほとんどは、妄想や思い込みなんかの取り越し苦労に過ぎないもの」
だと話されています。
たしかに心を落ち込ませていた悩みが、
客観的に見れば「なんでもないことであった」のは、
誰しも経験があると思います。
「間違えて先輩にタメ口を使ってしまった…」
「招待されたのに場違いな服装で来てしまった…」
自分は「やってしまった」と後悔しているのに、
それがきっかけで会話が弾んだり、逆に相手から褒めてもらえたりすると、
悩んでいた自分が馬鹿らしくまた、恥ずかしくなったりします。
このように不安や悩みがあったとしても、
相手の「ふとした言葉や行動」がきっかけで、
自分の心が軽くなることは意外とあるものです。
そして、禅の教えとは、そんなきっかけの宝庫です。
昔から私たちの生活と深い関わりを持った禅の教えを学ぶことで、
自分の考え方がガラッと変わって、ものごとの見え方や捉え方も変わってきます。
すると、自分の心の持ち方に余裕が生まれてくるのです。
4つの禅の教え
ここからは、仕事での不安や悩みを軽くする4つの禅語について解説します。
①莫妄想(ばくもうそう):妄想することなかれ

突然ですが、
不安や悩みや妬みが、なぜ生まれてしまうのかご存知でしょうか?
それは、「妄想」をしてしまうからです。
禅のなかの妄想とは、一般的な意味よりも広い意味があります。
「心を縛っているもの」「棲みついて離れないもの」
は、全て禅のなかでは妄想として扱われます。
「同期の方が自分より早く出世した」という妬みも、
「人前でうまく話せない」という自分への嫌悪も
全て禅では妄想です。
そして、仕事をしていると、このような妄想は必ず起こるはずです。
また、妄想が妄想を生んで、さらに気が滅入いるなんてこともあると思います。
しかし、極端なはなしですが、
この妄想を「0」に近づければ、このような不安や心配事がなくなります。
「莫妄想」は、まさにその教えを説いた禅語ですが、
実現させるのは、なかなか難しいことだと思います。
ですので、何とか妄想を0に近づけることができるように、
「妄想を生み出す根本的な原因は何か?」をまず考えていきます。
妄想は対立的な考え方から生まれる
妄想を生み出す原因とは、
ものごとを対立的にとらえてしまう考え方です。
「良い・悪い」「好き・嫌い」「偉い・偉くない」「高い・低い」「幸せ・不幸せ」
どれも対立的な考え方ですが、
私たちは、普段からものごとをなんでも対立的に考えてしまいがちです。
「昇格試験に自分だけが落ちてしまうなんて…」
「こんな事務作業にここまで時間がかかってしまうなんて…」
誰が判断したわけでもなく、
自分の判断基準でものごとの優劣を決めてしまいます。
そして、この考え方こそが妄想を生み出す原因です。
特に自分が不利な状況になる妄想を抱いてしまうときに、
心配や悩み、不安などのネガティブな感情になってしまいます。
比べない生き方をしよう
禅語に悟無好悪(さとればこうおなし)という言葉があります。
人間関係に寄せて意味を言えば、
「他の人がどうであろうと、あるがままを認めたら、好きとか嫌いとか、自分に比べて相手が上とか下とかの感情に流されることはない」
という意味です。
同期が自分よりも早く出世したのは、
会社が自分をおとしめようと考えていたり、
嫌いだからという理由ではないはずです。
同期の頑張りが実った結果であったり、
たまたまその機会に巡り会えただけかもしれません。
事務作業に時間がかかりすぎるのも、
その作業をするのが苦手などの理由があるかもしれません。
決して自分が非難されているわけではないはずです。
禅では、
どんなものも、どんな人も他と比べることはできない「絶対」の存在
として考えます。
本来、自分と他人は比べることができないはずなのに、
無理に比べようとするから余計な不安や悩み、妬みがついてくるのです。
仕事をしていると、自分を何かを比較して考える機会があるはずです。
しかし、そこには上下・優劣などの対立的な考え方はなく、
自分の行いや頑張り、努力の結果だけしか存在しません。
まずは目の前のことに全力で向き合っていれば、
おのずと不安や心配は減っていくのです。
- 莫妄想:心配事の原因の妄想を減らそう
- 悟好悪無:比較しなければ良し悪しなどの感情は生まれない。信じるのは自分のみ
②色眼鏡を外す:偏見や固定観念にとらわれない

職場の人間関係で悩んでいる方は多いと思います。
実際にアドラー心理学では、
「心にのしかかる不安や悩み、心配ごとのすべては対人関係」
とまで言っています。
そして、人間関係の悩みは、なかなか抜け出しにくい特徴があります。
なぜなら、相手に一度でも負の感情を持ってしまうと、
なかなか払拭することができないからです。
それどころか、その感情はますます悪化しさえします。
たとえば、会社の会議でA課長と少し意見が対立して、
「A課長とは話が合わない」
と思ったとします。
そのときの感情は、相手の一面から受けたものでしかないのに、
「色眼鏡」をかけて相手をみてしまい、
良からぬ先入観を持ってしまうものです。
そして、先入観は根強く心に棲みつきます。
すると今度は、
「A課長の人間性を疑ってしまう」
という考え方に変貌していきます。
禅では「色眼鏡をかけない」と言い、
人を先入観のみで判断することを戒めています。
その人の情報やある一面だけを見て、嫌な感情や否定的な思いを持ってしまい、
人間性を全否定してしまったら、その人を見誤ってしまうからです。
あらゆるものに仏性が宿っている
禅語に「一切衆生、悉く仏性有り」という言葉があります。
「あらゆるものには、仏性という仏になる可能性の美しい心がある」
という意味です。
もしかするとA課長は、
知らないところでみんなの仕事を引き受けているかもしれません。
ドラえもんに出てくるジャイアンは、普段はいじめっ子ですが、
妹やのび太がピンチになった際はすぐに助けにはいったりします。
このように誰にも「美しい心」があります。
良からぬ感情や先入観に直面した際に、
「自分が感じたのは、その人のほんの一面に過ぎないことで、今度は相手の中の仏性を見つけよう」
そう思うことで、人間関係の悩みは軽くなります。
もし誰かを好ましくないと思ってしまったなら、
実は色眼鏡をかけた自分がいるのではないかと思ってみましょう。
そして、その相手の仏性が分かり始めると、
人間関係の悩みも、「いつのまにかどこかに行ってしまった」
となるはずです。
- 一切衆生、悉く仏性有り:誰しも仏性という美しい心を持っている
- 色眼鏡をかけない:ある一面や情報だけでその人を見ないこと
③日日是好日(にちにちこれこうにち):良い日も悪い日も自分にとってはかけがえのない一日である

心配性さんにとって、環境が変わることほど心臓に悪いものはありません。
「え、来月から地方の営業所に転勤ですか?」
「え、今と違う職種の部署に異動ですか?」
思いもしない境遇に置かれそうになると、
不安でいっぱいになります。
私も過去に何度もこの経験をしていますし、
むしろ希望の部署へ異動できたことがありません。
そうなると不安半分と、
「なんで私が!」と怒り半分の気持ちになってしまいます。
たしかに「諸行無常」とう言葉あるように、
自分を取り巻く環境は常に変化していくものです。
それが仕事であろうと、家庭のことであろうと全部同じで、
これが自然法則なのは理解できます。
しかし、そうは言っても変化には良い変化と悪い変化があります。
「昇進」や「都市圏の転勤」などの良い変化は喜んで受け入れますが、
「降格」や「人気のない部署への異動」などは受け入れにくいものです。
本書ではそんな方に向けて、
「日日是好日」という禅語を紹介しています。
日日是好日」
これは毎日が良い日ばかりという意味ではなく、人生には晴れの日も雨の日もあります。
穏やかな日差しに包まれることもあれば、吹き付ける寒風に身をすくめることもあります。
しかし、いずれの日も、あなたはその日でなければできない実体験をする、かけがえのない経験を積む。
ですから、すべてが有意な「好日」なのです。引用:心配の9割は起こらない P87
「環境が自分を決めるのではなく、自分の生き方しだいでどんなものにでもなる」
という意味です。
どんな境遇にあっても自分を活かすことができるし、それが将来生きてくる
松下幸之助さんの言葉に、
「逆境もよし、順境もよし、要はその与えられた境遇を素直に生き抜くことである」
があります。
どんな境遇にあっても、自分がどう頑張れるかを考え実践することで、
それが将来の飛躍のバネにもなるし、生きる糧にもなるということです。
たとえば、今の職場と全く違う経理部に飛ばされたとしても、
経理で培ったコスト意識はどの部署でも役立つはずです。
私自身も、希望もしていない部署へ異動になった頃、
やけくそになって営業して作った人脈や営業スキルが
今は活かされているような気がします。
このように、素直に「今」を生きていけたら、
良い境遇も悪い境遇もないことが分かります。
あるのは、ただ一生懸命に生きるための「場所」があるだけです。
もし、今と環境が変わる場面に出会ったら、
「ここで何を頑張ることができるのか」を考えてみるようにしましょう。
今は見えないですが、
それが将来何かのかたちとなって自分にプラスに働くはずです。
- 日日是好日:良い日も悪い日も、その日でなければできない体験、経験を積むことができる一日。そういった意味では毎日が「好日」である
④心施(しんせ):自分の時間を割いて相手の心に寄り添う

心配性さんでなくても、
あなたの周りにも不安や悩みを抱えている方は必ずいるはずです。
そんな時に、自分ができることは、
そんな人たちの話を聞いて寄り添ってあげることです。
ここ数年でリアルの対話よりも、
メールやチャットが、主流なコミュニケーションの1つになってきました。
相手の顔が見えず、本来の対話の機会が失われることは、
以前よりも不平不満がたまりやすくなったかと思います。
社内のふとした雑談から、
お仕事やプライベートの会話まで発展して、
「言いたいことが言えた」なんて経験をしたことがあると思います。
すると、心のなかがすっきりして、
「次も頑張ろう」と思えるものです。
このように、たまには誰かに愚痴を聞いてもらうことは、
メンタルを正常に保つうえで重要なことです。
また、誰かの愚痴を聞いてあげることも時には必要なことだと思います。
「心施」という禅語があります。
「大切な自分の時間を割いて、相手のために心を配り思いやる心を持つ」
という仏道修行のなかの1つです。
つまり、相手の愚痴を聞くことも心を磨くこととなり、
自分の人間の度量を広げることにつながるのです。
清明風月を拂い、明月清風を拂う:人間関係は、持ちつ持たれつが大切
愚痴を聞く際に、重要なのは「聞き方」です。
相手の話の腰を折ったり、話の流れを止めてしまうのは、
良い聞き方ではありません。
また、相手の言っていることに相づちを打ったり、
感想を交えて共感することも、聞き方のなかで重要です。
相手もこちらがきちんと聞いていることが分かったら、
愚痴の言いがいがあって、ストレス解消の効果が高くなります。
そんなうまい聞き役に自分がまわることができたら、
いつかは相手がそのお返しをしてくれる日がくるかもしれません。
「今日くらいは自分も愚痴をこぼしたいな」
と思ったその時に、徹底して聞き役に回ってくれる人が現れると思います。
このように人間関係は、持ちつ持たれつでなんとかやっていくものです。
「清明風月を拂い、明月清風を拂う」とういう禅語は、
「さわやかに吹く風と明るく輝く月はそれぞれが美しくて、時にお互いが主となったり、客となったりしながら美を高めあっている」
という意味があります。
人間関係で言えば、
「人は付き合っている人に生かされ、またその人を生かしている」
ということです。
愚痴を言い合える人間関係を作っていくこと、
そのためにはまずは相手の愚痴の聞き役になってあげることが、
心配ごとや不安をためないコツの1つなのです。
- 心施:相手の心に寄り添う時間を作ること
- 清明風月を拂い、明月清風を拂う:愚痴を言い合える人間関係になることがストレスをためない生き方につながる
本書を読んだ感想
禅語の存在は昔から知っていたものの、
見聞きするなど実際に触れたことはありませんでした。
しかし、本書で禅語にはじめて触れて思ったのが、
「確かにそうだよなぁ」
という納得感でした。
禅語は私たちの生活に繋がりがあると言われているように、
意味合いの説明も、日常のたとえ話がふんだんに使われています。
それを読んだ後は、
普段の日常生活の中で私が当たり前に感じていたものごとの見え方が変わります。
私の場合は、ガラッと変わるくらい変わりました。
このガラッと変わることで、
「この教えはこれから実践してみよう」という気持ちになりましたし、
そのきっかけは、今回紹介できていないものも含めてたくさんありました。
著者は禅語をかみ砕いて、私たちに分かりやすく解説していますので、
一つ一つの禅語がスッと理解できるのも良かったです。
気になった方は、ぜひ読んでみてください。
最後までお読みいただき、ありがとうございました。
これからもブログの記事向上に向けて投稿を続けていきます。
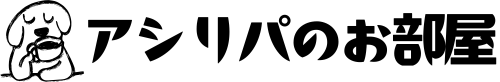
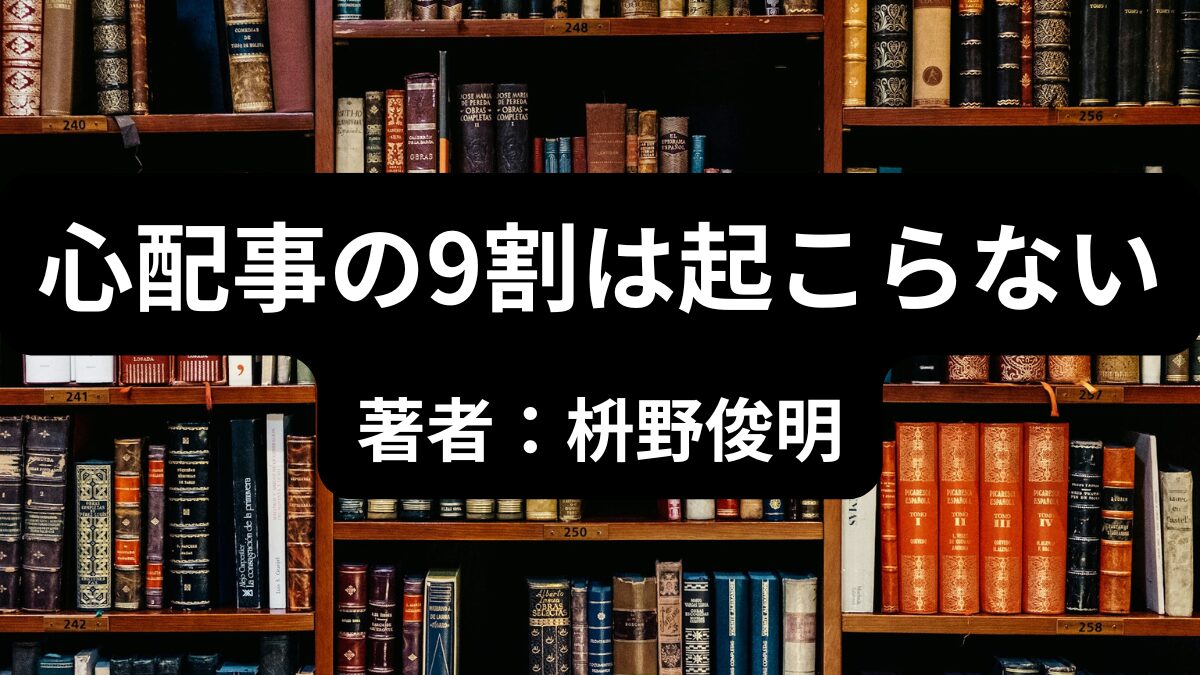



コメント